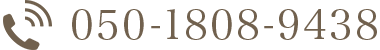この遺伝的な体質に環境要因が加わって初めてバセドウ病や橋本病を発症すると考えられています。
バセドウ病では強いストレスや喫煙、妊娠・出産、感染など、橋本病では強いストレスやヨウ素過剰摂取、妊娠・出産、感染などをきっかけに発症すると考えられています。
つまり、バセドウ病や橋本病を発病しやすい体質を受け継いだからといって、必ず発症するというわけではありません。
バセドウ病や橋本病は思春期以降に発症することが多いため、気になる方はこの頃に一度調べるのがよいでしょう。
思春期以前では、子どもの発達や成長に問題がなければ、特に心配はありません。
バセドウ病を発症すると「頻脈、微熱、発汗増加、手の震え、疲れやすさ、体重減少、食欲亢進、排便回数の増加」などの甲状腺ホルモン過剰に伴う症状や「甲状腺の腫れ、眼球突出」がみられますが、特に小児では「身長の伸びが速くなる、落ち着きがなくなる、学力や運動能力が低下する」などの変化が現れることがあります。
橋本病では甲状腺の腫れや甲状腺機能低下の症状が認められますが、「身長の伸びが急に悪くなる」ことも小児期発症の橋本病に特有な症状です。
このような兆候があれば、小児科などで甲状腺の検査を受けることをお勧めします。